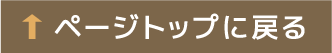子どもの叱り方 NPOハート・コンシャス
お問い合わせ
TEL. 0586-72-7880
営業時間 AM10:00 ~ PM18:00

子どもの叱り方
NPOハート・コンシャスの理事でもある鷲津先生(名城大学心理学非常勤講師、(同)ベルコスモ・カウンセリング代表)に伺いました。
私たちNPOハート・コンシャスの理事でもある鷲津先生(名城大学心理学非常勤講師、(同)ベルコスモ・カウンセリング代表)に伺いました。
今回は【叱る】ということについて伺いたいと思います。
まず、よく『叱るより褒めろ』って言いますよね。
「はい。これは本当ですね。『叱る』のも『褒める』のも、【親が期待する言動を、子どもにしてもらう手段】なんですが、『叱る』よりも『褒める』方が、圧倒的に効果が大きいんですね」
------効果が大きい…。
 「ええ。これは色々なテストではっきりと出ています。例えば『叱る』というのは『褒める』よりも、慣れやすいんです。これを馴化と言うんですけど」
------あ、わかります。
最初のうちは聞いてますけど、何回目かになると、もう聞いていないですもんね。
「そうなんですよ。それに引き替え『褒められる』というのは、何度でもうれしいんですね。あと、『叱る』というのは『期待した方向に進まない』場合があるんです」
------と言いますと?
「例えば『寝る前に歯を磨く』ようになってほしかったとしますね。この場合、磨かなかった時に叱るとします。そうすると、磨くようになってくれればいいのですが、磨いたふりをするとか『叱られないように努力する』場合があるんですよ(笑)」
------そんな努力をする暇が有ったら、磨いてくれればいいのに…。
「親はほんとにそう思いますよね。ところが『磨いた時に褒める』というのは、こういう問題は出てきません。それとね、もう一つ厄介な問題が有るんです。『叱る』と、【その事が嫌いになる】ことが多いんです」
------あ、なるほど!
『歯を磨きなさい!』って叱ると、歯を磨くことが嫌いになると…。
「そういうことです。ところが『褒められる』と、そのことが好きになる可能性が高くなるんですね」
------う~~ん、そういうことですか。
「そういうことです」
「ええ。これは色々なテストではっきりと出ています。例えば『叱る』というのは『褒める』よりも、慣れやすいんです。これを馴化と言うんですけど」
------あ、わかります。
最初のうちは聞いてますけど、何回目かになると、もう聞いていないですもんね。
「そうなんですよ。それに引き替え『褒められる』というのは、何度でもうれしいんですね。あと、『叱る』というのは『期待した方向に進まない』場合があるんです」
------と言いますと?
「例えば『寝る前に歯を磨く』ようになってほしかったとしますね。この場合、磨かなかった時に叱るとします。そうすると、磨くようになってくれればいいのですが、磨いたふりをするとか『叱られないように努力する』場合があるんですよ(笑)」
------そんな努力をする暇が有ったら、磨いてくれればいいのに…。
「親はほんとにそう思いますよね。ところが『磨いた時に褒める』というのは、こういう問題は出てきません。それとね、もう一つ厄介な問題が有るんです。『叱る』と、【その事が嫌いになる】ことが多いんです」
------あ、なるほど!
『歯を磨きなさい!』って叱ると、歯を磨くことが嫌いになると…。
「そういうことです。ところが『褒められる』と、そのことが好きになる可能性が高くなるんですね」
------う~~ん、そういうことですか。
「そういうことです」
絶対に叱っちゃいけないのか?
------じゃあ、絶対に叱っちゃいけないっていうことですか? 「いえ、本やセミナーでは、『子どもを絶対に叱っちゃいけない』という言葉がよく出てきますが、僕はそうは思っていません」 ------え? そうなんですか? 「はい。まず第一に、叱ることで効果のある子どものタイプがあるんですね」 ------叱っても効果がある? 「ええ。例えば子どもの中でも成績が良い子は、叱っても効果がある場合もあるんです」 ------と言うことは、悪い子は…。 「これは、もう『叱るより褒めろ』です。『叱る』と、かえってやる気を無くしたり自己評価が益々低くなったり、本当にデメリットが多いんですよ」 ------なるほど。 「また、外向的な子どもの場合にも叱っても効果がある場合が認められます」 ------と言うことは、内向的な子はやっぱり…。 「そういうことですね。先程のケースと一緒です。 つまり『成績が優秀で外向的』な子どもは、叱っても効果がある場合もありますが、但しもちろんその場合でも『叱るより褒めろ』んなんですけどね、『成績があまり良くなく内向的』な子どもに対しては、叱るということは本当にデメリットが大きいんです」 ------でも、ちょっと待ってくださいよ! わたし達って逆をやってません? つまり、『成績が優秀で外向的』な子どもは褒めて、『成績があまり良くなく内向的』な子どもを叱っちゃう…。 「そこなんですよ、問題は。結構、自己評価の低い子どもって、このケースが多いんですね」
------じゃあ、そういう子どもは絶対に叱っちゃいけないですね。
「ところが、親としては叱りたくなっちゃうんですよね。そこで大事なのが【叱り方】なんです」
------よく、『感情的に叱ってはいけない』って言いますよね。
「そうですね。そしてそれは確かにその通りなんです。ただね、我々は神様でもなければ仏様でもないんです。そう簡単に『怒りを制御』できたら苦労はないんですよね」
------そうなんです!
だから、是非知りたいんですよね、『叱り方』を。
「はい。ただその前に、叱る時というのは『~してほしいのに、してくれなかった』、若しくは『~してほしくないのに、された』という場合が殆どなんですね」
------そうですね。
「という事は、順序として、まず叱るのではなく『~してほしい』とか『~してほしくない』ということを、わかりやすくはっきりと伝えるのが大事ですよね」
------なるほど。親の考えが子どもに明確に伝わっているかどうかの確認ということですね。
「そういうことです。できたらこれは、文として書いておいた方がいいですね」
「そこなんですよ、問題は。結構、自己評価の低い子どもって、このケースが多いんですね」
------じゃあ、そういう子どもは絶対に叱っちゃいけないですね。
「ところが、親としては叱りたくなっちゃうんですよね。そこで大事なのが【叱り方】なんです」
------よく、『感情的に叱ってはいけない』って言いますよね。
「そうですね。そしてそれは確かにその通りなんです。ただね、我々は神様でもなければ仏様でもないんです。そう簡単に『怒りを制御』できたら苦労はないんですよね」
------そうなんです!
だから、是非知りたいんですよね、『叱り方』を。
「はい。ただその前に、叱る時というのは『~してほしいのに、してくれなかった』、若しくは『~してほしくないのに、された』という場合が殆どなんですね」
------そうですね。
「という事は、順序として、まず叱るのではなく『~してほしい』とか『~してほしくない』ということを、わかりやすくはっきりと伝えるのが大事ですよね」
------なるほど。親の考えが子どもに明確に伝わっているかどうかの確認ということですね。
「そういうことです。できたらこれは、文として書いておいた方がいいですね」
「面倒」が問題
------それでも言うことを聞かなかったら? 前に出た例ですけど、食後に歯を磨かないとか。 「そうなんですよね。伝えてもなかなかやってくれないのが、子どもなんですよね。でもどうしてやってくれないんでしょう?」 ------面倒だからじゃないですか?(笑) 「そうなんですよ! そのとおりなんです。わかってるじゃないですか! じゃあ、どうしてそういう時に『何でやらないの!』って怒るんでしょうね~(笑)」 ------あ、そう言われるとそうですね。 何の意味もないですね、『何でやらないの!』って怒り方は。 「そのとおりなんです。意味がないことを言ってお互いが不愉快になっているんですよね。だからそれよりも、『面倒な事をやったら、その面倒さを上回る【得】をするシステム』を作った方が早いんです。 逆に言うと、『やらないと、得られるモノが得られなくなってしまうシステム』ですね。これが【効果的な叱り方】なんですよ。これを具体的に考えていくのが大事なんです」 ------う~ん、なんか面倒なんですね~。 「面倒でしょ? でもよく考えてくださいね。『子どもに面倒なことをやってもらう』んでしょ?」 ------なるほど!(笑) 親がめんどくさがっていちゃ、話にならないですね。 「そうですね。ところでまずは順序としてそこから話してきましたが、僕としてはそういうやさしいやり方だけではなく、厳しい叱り方も実は大事じゃないかと思うんです。例えば僕には娘がいるのですが、小さい時に厳しく叱ったのは【健康】と【安全】に関わる時と決めていたんですね。 眼が悪くなるような姿勢で本を読んでいたり、近所で遊んでいる時に道路へ飛び出したりした時とか…」 ------なるほど。 『こういう事に関しては、叱るよ』と。 「そういう事です。だから、大事なのはルールを作ることだと思うんですね。そうなると、まず第一に考えないといけないのは、【ルールの明文化】です。 例えば、日本という国で考えると憲法が有り、刑法が有り、民法や商法がありますよね。そしてそれに反するとその法律に明記されている量の罰が与えられます」 ------どういう事をしたらいけないか、またそれをするとどういう罰が与えられるかをはっきりしておくという事ですね。 「ええ。その時その時の親の気分しだいで罰を変えてはいけないということです。そしてその罰も合理的なものでないといけません」 ------『叱る』には【明確さ】が必要だと。 「はい。これが出来ていると、意外と子どもって叱られても納得してくれるものなんですよ。ただこれについては大事なことが一つあるんです。レディネスの問題なんですね」 ------レディネスの問題と言いますと? 「器(うつわ)の問題と言ってもいいでしょう。例えば算数をやるには、数字というものの概念が既に無ければ無理ですよね。それと一緒です。 器がまだ出来ていないと、いくらルールを作ってもうまくいかない場合が有ります。例えば『人に迷惑をかけない』というルールを作って明文化したとしても、5~6歳にならないと、この概念は子どもにはわからないんです」 ------あ、なるほど。 じゃあ3歳の子どもに、いくら『人に迷惑をかけてはいけない』と叱っても、無理があるということなんですね。 「そうなんですね。それと、もし子どもを叱った場合は、できるだけそれをノートか何かに書き留めていただきたいんです」 ------『怒った事ノート』ですか。 「そうです。それをやって、たまに内容を整理していただくと、気づく事がとっても沢山あるんですね。また、それを系統だてていくと知らないうちに『叱るのが上手』になっていくんです」 ------へぇ~、そうなんですか! いいですね!『叱るのが上手』って。 是非、なりたいです。 「なってください(笑)」この内容はNPOハート・コンシャス顧問の鷲津秀樹先生へのインタビューや、大学での講義の内容を元に書いております。
著作権は合同会社ベルコスモ・カウンセリングにあります。ご了承ください。

好評発売中の子育て心理学
 「もっと早く知りたかった」と言われる子育て心理学
「もっと早く知りたかった」と言われる子育て心理学~応用行動分析・交流分析~」 鷲津秀樹著 (お求めはアマゾンで↑) この本はNPO日本次世代育成支援協会の心理学セミナーなどにおいて、発達障碍についてお話した内容をまとめたものです。 子育てに役立つ応用行動分析を、セミナーの講義のように口語形式で図を交えながらわかりやすく書いてあります。
大分大学地域連携プラットフォーム推進機構」主催のセミナー
 大分県立看護科学大学、日本文理大学、別府大学、立命館アジア太平洋大学、大分県立芸術文化短期大学、大分短期大学、東九州短期大学、別府溝部学園短期大学、別府大学短期大学部、大分工業高等専門学校、放送大学大分学習センター、大分大学で構成される「大分大学地域連携プラットフォーム推進機構」主催のセミナーの講師として、各校の教職員の方々対象にWEBで講演しました(鷲津秀樹)。
(翌週13日は大分大学単独で先生方への講演)
大分県立看護科学大学、日本文理大学、別府大学、立命館アジア太平洋大学、大分県立芸術文化短期大学、大分短期大学、東九州短期大学、別府溝部学園短期大学、別府大学短期大学部、大分工業高等専門学校、放送大学大分学習センター、大分大学で構成される「大分大学地域連携プラットフォーム推進機構」主催のセミナーの講師として、各校の教職員の方々対象にWEBで講演しました(鷲津秀樹)。
(翌週13日は大分大学単独で先生方への講演)日本製鉄労働組合 組合員研修セミナー
 日本製鉄の労組組合役員・職場評議員・関係協力会社労組の各労組役員の方を対象としたメンタルヘルス研修セミナーにおいて、「メンタルヘルスとコミュニケーション」というテーマの講演を務めました。
日本製鉄の労組組合役員・職場評議員・関係協力会社労組の各労組役員の方を対象としたメンタルヘルス研修セミナーにおいて、「メンタルヘルスとコミュニケーション」というテーマの講演を務めました。
愛知県保険医協会「子どもの健康を考えるつどい」
 愛知県保険医協会主催の「第34回 子どもの健康を考えるつどい」において、「コロナ禍が及ぼす子どもたちの心への影響と、その対処法」というテーマで講師を務めました。
愛知県保険医協会主催の「第34回 子どもの健康を考えるつどい」において、「コロナ禍が及ぼす子どもたちの心への影響と、その対処法」というテーマで講師を務めました。ネット・スマホ・ゲーム依存防止講演についてはこちら↓・
https://npo-jisedai.org/izonkouen.html