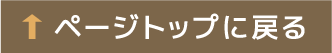劣等感とコンプレックスと低い自己評価 心理カウンセリング(認知行動療法) 愛知・岐阜・三重 電話カウンセリング(電話代不要)、ネットカウンセリングも可
お問い合わせ
TEL. 0586-72-7880
営業時間 AM10:00 ~ PM18:00

劣等感とコンプレックスと低い自己評価・カウンセリング
まずは、劣等感とコンプレックスの違いについて。
劣等感というのは、字のごとく「自分は劣っている」という感情です。
そして、それは意識されているということになりますよね。
ではコンプレックスはというと、これも自分の『劣っている部分』についての悩み、と思っている人が多いようですが、実は『無意識に感じている複雑な思い』と言ったほうがいいんですね。
ただ、一般的にはゴチャマゼに使われている場合が多いので、ここではあまり気にせず話を進めていくことにします。
さて、その劣等感ですが、自分の何か、例えば学校の勉強ができないという事にしましょうか。
その場合、テストで低い点数を取っていて、劣等感とか劣等コンプレックスという感情が生じたとします。
でも、その場合、人は『何に比べて』、『どれだけ劣っている』か、つまり劣っていると判断する【基準】を、あまり考えていないことが多いんですね。
例を挙げてみましょう。
アインシュタインより頭が悪いからといって、悩む人は殆どいません。
白鵬より相撲が弱くっても、別に平気なはずです。
…という事は、自分と比較する基準が高すぎる場合は、劣等コンプレックスは生じません。
どちらかと言うと、周囲の自分と近いゾーンで比較しているはずです。
しかも、人はこの基準を『自分で設定』している場合が多いんですね。
例えば、自分も超難関校の私立大学に行っているのに、お兄ちゃんが東大に行っていて、しかも子どもの頃から親にその兄と比較ばかりされて怒られていた場合は、勉強において劣等コンプレックスを持ってしまうということがあります。
 考えてみると、結構おかしな話で悩んでいるんですよ。
自分で勝手に非合理的な基準を設定し、それよりも低いと【劣等感】、高いと【優越感】を感じて一喜一憂しているという事ですから。
基準をどこに設定しているのか?
設定したのは誰で、自分がその基準を適正と判断した根拠は何か?
これらをじっくりと考えてみると、「あれっ?」って思える部分が出てくるはずです。
実際、何に対して何を基準とするかにおいて、勘違いしている人って本当に多いんですよね。
例えば学校で使う偏差値がそうです。
あれは、記憶力や計算能力とかを比較する基準であって、人間性とか信頼性とは関連が有りません。
なのに、偏差値を基準として他人を【信じる】人っているでしょ?
以前、一流と言われている某大学の学生が殺人事件を起こしたときに、「あんな良い大学へ行っているのに、どうして?」という声が沢山上がりました(メディアでもそんなことを書いていたところがあったのには驚きました)。
その大学は確かに、入試の際にすごく高い偏差値をクリアしないと入れないけど、その大学の入試には『人間性のテスト(やさしさのテスト)』とかは無いんですよ。
入試の偏差値で『やさしさ』を計るなんて、体重をモノサシで計っているようなものです。
100m競争で、早い人から順に頭が良いって言ってるのと同じような事なんですよ。
そんなおかしな話なんかに巻き込まれて、劣等感なんか持ってしまったら悲劇ですものね。
考えてみると、結構おかしな話で悩んでいるんですよ。
自分で勝手に非合理的な基準を設定し、それよりも低いと【劣等感】、高いと【優越感】を感じて一喜一憂しているという事ですから。
基準をどこに設定しているのか?
設定したのは誰で、自分がその基準を適正と判断した根拠は何か?
これらをじっくりと考えてみると、「あれっ?」って思える部分が出てくるはずです。
実際、何に対して何を基準とするかにおいて、勘違いしている人って本当に多いんですよね。
例えば学校で使う偏差値がそうです。
あれは、記憶力や計算能力とかを比較する基準であって、人間性とか信頼性とは関連が有りません。
なのに、偏差値を基準として他人を【信じる】人っているでしょ?
以前、一流と言われている某大学の学生が殺人事件を起こしたときに、「あんな良い大学へ行っているのに、どうして?」という声が沢山上がりました(メディアでもそんなことを書いていたところがあったのには驚きました)。
その大学は確かに、入試の際にすごく高い偏差値をクリアしないと入れないけど、その大学の入試には『人間性のテスト(やさしさのテスト)』とかは無いんですよ。
入試の偏差値で『やさしさ』を計るなんて、体重をモノサシで計っているようなものです。
100m競争で、早い人から順に頭が良いって言ってるのと同じような事なんですよ。
そんなおかしな話なんかに巻き込まれて、劣等感なんか持ってしまったら悲劇ですものね。

好評発売中の「心の本」
 「ハートの免疫力UP!」認知療法と解決志向アプローチ
鷲津秀樹著 (お求めはアマゾンで↑)
この本は、このページの筆者が大学の講義(心理学)のテキストとしても使用していた、認知療法や解決思考アプローチをわかりやすく解説した図書です。
「ハートの免疫力UP!」認知療法と解決志向アプローチ
鷲津秀樹著 (お求めはアマゾンで↑)
この本は、このページの筆者が大学の講義(心理学)のテキストとしても使用していた、認知療法や解決思考アプローチをわかりやすく解説した図書です。
劣等感と優越感は同じ袋の中に有る
さて、人間は【理想自我】というものを持っています。 『自分はこうありたい』 とか 『自分はこのようになりたい』 というのがそれです。 これは、適度であれば結構なモノなのですが、それこそこれに【執着】してしまうと大変なんですね。 その【理想イメージ】から、現実の今の自分を引き算して、「自分が嫌い」なんて言っていてもしょうがないんじゃないかと思うんですけど。(下図) そうではなく、それは将来における理想として、目標として一段ずつそれに向かって進んでいくというなら、それはとっても素晴らしいこととなります。(下図)
そうではなく、それは将来における理想として、目標として一段ずつそれに向かって進んでいくというなら、それはとっても素晴らしいこととなります。(下図)
 僕はよく『人に好きになってもらうには、まず自分が自分を好きじゃないと…』って言っています。
自分でも嫌いな自分を、人に好きになってくれというのは無理がありますからね。
ところが、勝手に自分の理想のイメージを想像して、それに現実の自分を比較して「自分を好きになれない」とか言って、挙句の果てに「どうして自分は人に好かれないんだろう」とか悩んで暗くなって、そして「あいつは暗いから」とか周囲から敬遠されたりして…。
その、「自分を好きになれない」というのは、自分を低く見ているということですけど、『何』に比べてなのかは、考えてみた方がいいでしょうね。
もちろん、理想の自分と比べるということだけではなく、他の人と比べて劣等感を持つ場合もあるでしょう。
平均という合理的な基準から比べて、低い場合もあると思います。
例えば、部分部分において劣等感を持ったり、自己嫌悪に陥ったりするという事は有ってアタリマエです。
人並みより背が低い、というのがわかりやすい例ですね。
でも、次の文を読んで、どう思われますか?
『日本人はフランス人よりもムードが無く、イタリア人よりも陰気である。
しかも、インド人よりも数学に弱く、ザイール人よりもマラソンで遅い。
その上ユダヤ人よりも商売がヘタで、アメリカ人のように前向きではない。
なんと言っても悲しいのは、アラスカ人より寒さに弱いくせに、なんとエチオピア人より暑さに弱いのだ。
よって、日本人は世界で最も情けない人種の1つである』
これを僕が言うと、『馬鹿馬鹿しい!』って笑う人が多いのですが、実は結構同じような考え方をして悩んでいる人って多いんですよ。
さて、劣等感で悩んでいる人は沢山います。
でも、そういう方々の中には、その反対に優越感を本人も気付かずに持っている場合が有ります。
ということは、劣等感と優越感は同じ袋の中に有ることが多いということなんですね。
先ほど言ったように、劣等感にしろ優越感にしろ、どこかに自分で基準線(合格点)を引くことで発生します。
その線以上なら優越感を抱き、その線以下なら劣等感に苛まれるというわけです。
…ということは、劣等感とか優越感に捉われない人は、あまり物事に厳格な、もしくは高邁な基準線や合格点を設定しない人と言えるんですね。
ところで、劣等感で悩んでいる人が特に気を付けなくてはならないのは、なにか一つに劣等感の対象を集中させ(例えば鼻の形が悪いとか)、そのせいでいろいろな事がうまくいかないと思い込み、深みにはまっていくことです。
整形手術をして鼻を高くしたら、きっとモテるようになるだろうし、きっと就職もうまくいくだろうし と思い悩むのは勝手です。
でも、整形手術をしたら、『鼻が高くなる』だけなんですね。
そうではなく、問題は自分の『下に見られるのが嫌』だと感じている【自分の心の部分にある】かもしれない、と考えると心が楽になるかもしれません。
自分で基準線を引き、そして苦しむ…。
理屈では馬鹿馬鹿しいとわかるのですが、ついついやってしまいがちな事ですね。
また、人から批判されて、落ち込んで劣等感が生じてしまう時がありますよね。
例えば人から「君は自分勝手だ!」と言われて、「わたしは自分勝手な人間なのだから人に好かれない」という劣等感が生じたとします。
でも、本当にそうでしょうか?
ちょっと例を挙げてみますね。
【通らないワガママ】ばかり言う人は<自分勝手>と言われます。
では【通るワガママ】を言う人は?
これは<自由奔放>って言われるんですね。
次に…。
【許せないワガママ】を言うと<大人気ない>と言われます。
では【許せるワガママ】を言う人は?
これは<少年の心を持つ人>って言われるんです。
おわかりいただけましたか?
『わたしは自分勝手な人間なのだから人に好かれない』のではないんですね。
『その相手にとって、【通らないワガママ】や【許せないワガママ】を言ったから、勝手と言われる』んです。
つまり【あなた】がいけないのではなく、【あなたの表現方法】や、勝手な思いをどこまで表現するかの【判断力】がイマイチな場合だって結構あるんですよ。
これらは【技術】の問題ですよね。
つまり上手な人を真似して練習すれば上達する、という事です。
ところで、カウンセラーというのは、『クライアントの心の鏡になれ』とよく言われます。
クライアントの心を、歪みや曇りなどないように写し出し、クライアントに『気付き』をもたらすという事でしょうね。
…と云うことは、当然カウンセラーはまずは自分の心を、歪み無く曇りもなく見つめることができなくてはなりません。
ここが難しいんですよね。
歪み無く曇りなく心を観ると、見たくない嫌なところが一杯出てくるんです。
例えば、人を褒めている自分だって、『いい人に見られたい』とか、『自分が得をしたいから褒めている』のかもしれません。
思わず「パス!」って、見ないで通り過ぎたいところがいくらでも出てきちゃうんですね。
じゃあ、どうすればいいのか。
その見たくないものをパスしたら、それはそれでいつまで経っても『気づき』は生まれないし、かと言って見たくないところを見てはそれを責めていたら、それこそ鬱になっちゃいます(うつ病の人に自責概念や自罰思考が多いというのは、この問題です)。
だからこそ、【しょうがない】という言葉が大事なんですね。
我々は神様や仏様じゃないんだから。
ところで、僕がこの『しょうがない』という言葉を使うと、「しょうがないで済ませるのは、逃げることになりませんか?」という質問をされることがあります。
確かに、「しょうがない」と言って、物事に向き合わずに逃げてる人もいます。
でもそれは、『自分の心を見つめずに「しょうがない」でフタをしちゃう人』なんですね。
そうじゃなしに、『しっかりと心を見つめて、そのうえで「しょうがないものはしょうがない」と許す』のが大事だと僕は思うんです。
そして、もし今まで見たくないからスルーしていた自分の嫌なところを、笑いのネタにできるようになれたら最高なんですけどね。
さて、まとめとなります。
冒頭の話に戻ってみましょう。
人は、自分の造った理想自我と比較して、自己嫌悪したり劣等感を抱いたりすることが多いんですね。
そして、自分では自分を『馬鹿にしている』くせに、人に馬鹿にされると怒りが湧いてきたりして…。
自分で勝手にいいトコ取りの理想の自分を作成し、それと現状の自分を比較して落ち込み、自信を無くし、自信の無いところへ人から何かを指摘されては、また自信を無くしては落ち込んでいるワケです。
もし、その負のスパイラルにはまりこんでしまったら…。
まずは現状の自分に対して『だってしょうがないもんね』と笑って言えることが大切です。
泣いて言ってちゃダメなんです。
どうしてか。
しょうがないものはしょうがないから。
悩んでいる暇が有ったら、その時間に自分の「売り」になるところを探しましょう。
「売り」になるところがない?
やったことがないことって一杯あるでしょ?(例えばリケンベっていう楽器を弾いたことあります?)
…ということは、やったことがないから出来ないということが一杯あるっていうことです。
だとしたら、やったら出来ることだって幾つもあるんじゃないですか?
そして、その中に長所があるかもしれません。
それを可能性って言うんですけどね。
人の魅力っていうのは【長所-短所=?】という式の『?』なんですよね。
この、『?』を大きくすることが大事なんです。
これが大きくなったら、その劣等感をいだいているものは、「しょうがない」から「それがどうした!」に変わっていきます。
いかがですか?
「それがどうした!」を目指していきませんか?
劣等コンプレックスの人に、カウンセリング効果もあるカウンセラー講座はこちら↓
https://npo-jisedai.org/kouza.htm
お役に立てる心理学の本です。↓
僕はよく『人に好きになってもらうには、まず自分が自分を好きじゃないと…』って言っています。
自分でも嫌いな自分を、人に好きになってくれというのは無理がありますからね。
ところが、勝手に自分の理想のイメージを想像して、それに現実の自分を比較して「自分を好きになれない」とか言って、挙句の果てに「どうして自分は人に好かれないんだろう」とか悩んで暗くなって、そして「あいつは暗いから」とか周囲から敬遠されたりして…。
その、「自分を好きになれない」というのは、自分を低く見ているということですけど、『何』に比べてなのかは、考えてみた方がいいでしょうね。
もちろん、理想の自分と比べるということだけではなく、他の人と比べて劣等感を持つ場合もあるでしょう。
平均という合理的な基準から比べて、低い場合もあると思います。
例えば、部分部分において劣等感を持ったり、自己嫌悪に陥ったりするという事は有ってアタリマエです。
人並みより背が低い、というのがわかりやすい例ですね。
でも、次の文を読んで、どう思われますか?
『日本人はフランス人よりもムードが無く、イタリア人よりも陰気である。
しかも、インド人よりも数学に弱く、ザイール人よりもマラソンで遅い。
その上ユダヤ人よりも商売がヘタで、アメリカ人のように前向きではない。
なんと言っても悲しいのは、アラスカ人より寒さに弱いくせに、なんとエチオピア人より暑さに弱いのだ。
よって、日本人は世界で最も情けない人種の1つである』
これを僕が言うと、『馬鹿馬鹿しい!』って笑う人が多いのですが、実は結構同じような考え方をして悩んでいる人って多いんですよ。
さて、劣等感で悩んでいる人は沢山います。
でも、そういう方々の中には、その反対に優越感を本人も気付かずに持っている場合が有ります。
ということは、劣等感と優越感は同じ袋の中に有ることが多いということなんですね。
先ほど言ったように、劣等感にしろ優越感にしろ、どこかに自分で基準線(合格点)を引くことで発生します。
その線以上なら優越感を抱き、その線以下なら劣等感に苛まれるというわけです。
…ということは、劣等感とか優越感に捉われない人は、あまり物事に厳格な、もしくは高邁な基準線や合格点を設定しない人と言えるんですね。
ところで、劣等感で悩んでいる人が特に気を付けなくてはならないのは、なにか一つに劣等感の対象を集中させ(例えば鼻の形が悪いとか)、そのせいでいろいろな事がうまくいかないと思い込み、深みにはまっていくことです。
整形手術をして鼻を高くしたら、きっとモテるようになるだろうし、きっと就職もうまくいくだろうし と思い悩むのは勝手です。
でも、整形手術をしたら、『鼻が高くなる』だけなんですね。
そうではなく、問題は自分の『下に見られるのが嫌』だと感じている【自分の心の部分にある】かもしれない、と考えると心が楽になるかもしれません。
自分で基準線を引き、そして苦しむ…。
理屈では馬鹿馬鹿しいとわかるのですが、ついついやってしまいがちな事ですね。
また、人から批判されて、落ち込んで劣等感が生じてしまう時がありますよね。
例えば人から「君は自分勝手だ!」と言われて、「わたしは自分勝手な人間なのだから人に好かれない」という劣等感が生じたとします。
でも、本当にそうでしょうか?
ちょっと例を挙げてみますね。
【通らないワガママ】ばかり言う人は<自分勝手>と言われます。
では【通るワガママ】を言う人は?
これは<自由奔放>って言われるんですね。
次に…。
【許せないワガママ】を言うと<大人気ない>と言われます。
では【許せるワガママ】を言う人は?
これは<少年の心を持つ人>って言われるんです。
おわかりいただけましたか?
『わたしは自分勝手な人間なのだから人に好かれない』のではないんですね。
『その相手にとって、【通らないワガママ】や【許せないワガママ】を言ったから、勝手と言われる』んです。
つまり【あなた】がいけないのではなく、【あなたの表現方法】や、勝手な思いをどこまで表現するかの【判断力】がイマイチな場合だって結構あるんですよ。
これらは【技術】の問題ですよね。
つまり上手な人を真似して練習すれば上達する、という事です。
ところで、カウンセラーというのは、『クライアントの心の鏡になれ』とよく言われます。
クライアントの心を、歪みや曇りなどないように写し出し、クライアントに『気付き』をもたらすという事でしょうね。
…と云うことは、当然カウンセラーはまずは自分の心を、歪み無く曇りもなく見つめることができなくてはなりません。
ここが難しいんですよね。
歪み無く曇りなく心を観ると、見たくない嫌なところが一杯出てくるんです。
例えば、人を褒めている自分だって、『いい人に見られたい』とか、『自分が得をしたいから褒めている』のかもしれません。
思わず「パス!」って、見ないで通り過ぎたいところがいくらでも出てきちゃうんですね。
じゃあ、どうすればいいのか。
その見たくないものをパスしたら、それはそれでいつまで経っても『気づき』は生まれないし、かと言って見たくないところを見てはそれを責めていたら、それこそ鬱になっちゃいます(うつ病の人に自責概念や自罰思考が多いというのは、この問題です)。
だからこそ、【しょうがない】という言葉が大事なんですね。
我々は神様や仏様じゃないんだから。
ところで、僕がこの『しょうがない』という言葉を使うと、「しょうがないで済ませるのは、逃げることになりませんか?」という質問をされることがあります。
確かに、「しょうがない」と言って、物事に向き合わずに逃げてる人もいます。
でもそれは、『自分の心を見つめずに「しょうがない」でフタをしちゃう人』なんですね。
そうじゃなしに、『しっかりと心を見つめて、そのうえで「しょうがないものはしょうがない」と許す』のが大事だと僕は思うんです。
そして、もし今まで見たくないからスルーしていた自分の嫌なところを、笑いのネタにできるようになれたら最高なんですけどね。
さて、まとめとなります。
冒頭の話に戻ってみましょう。
人は、自分の造った理想自我と比較して、自己嫌悪したり劣等感を抱いたりすることが多いんですね。
そして、自分では自分を『馬鹿にしている』くせに、人に馬鹿にされると怒りが湧いてきたりして…。
自分で勝手にいいトコ取りの理想の自分を作成し、それと現状の自分を比較して落ち込み、自信を無くし、自信の無いところへ人から何かを指摘されては、また自信を無くしては落ち込んでいるワケです。
もし、その負のスパイラルにはまりこんでしまったら…。
まずは現状の自分に対して『だってしょうがないもんね』と笑って言えることが大切です。
泣いて言ってちゃダメなんです。
どうしてか。
しょうがないものはしょうがないから。
悩んでいる暇が有ったら、その時間に自分の「売り」になるところを探しましょう。
「売り」になるところがない?
やったことがないことって一杯あるでしょ?(例えばリケンベっていう楽器を弾いたことあります?)
…ということは、やったことがないから出来ないということが一杯あるっていうことです。
だとしたら、やったら出来ることだって幾つもあるんじゃないですか?
そして、その中に長所があるかもしれません。
それを可能性って言うんですけどね。
人の魅力っていうのは【長所-短所=?】という式の『?』なんですよね。
この、『?』を大きくすることが大事なんです。
これが大きくなったら、その劣等感をいだいているものは、「しょうがない」から「それがどうした!」に変わっていきます。
いかがですか?
「それがどうした!」を目指していきませんか?
劣等コンプレックスの人に、カウンセリング効果もあるカウンセラー講座はこちら↓
https://npo-jisedai.org/kouza.htm
お役に立てる心理学の本です。↓
 |
「ハート・コンシャス」~ 交流分析・認知療法・実存セラピー~ 鷲津秀樹著 1760円 心理カウンセリングに役立つ交流分析や周辺理論がとてもわかりやすく書かれている本です。 著者が名城大学の講義でも使っている本で、大学内の書店か通販以外ではお求めになれません。 お買い求めは、ここをクリック! https://bellcosmo.net/hon.html |
でも、『来てみたら、意外にすんなり話せたし心が楽になった』と仰る方が殆どです。 『一度、試しに行ってみようか』という感じでカウンセリングを受けてみては如何ですか? カウンセリングとはカウンセラーがクライアントと一緒に、一生懸命悩んで考える場です。 遠方の場合は無料テレビ電話でのWEBカウンセリングも可能です。
悩みは一人一人が違います。 したがってカウンセリングはクライアントに合った方法を取ります。 例えばうつ病や不安障害(不安症)には、認知療法が効果がありますし、子育ての悩みだと応用行動分析が適しています。 また、不登校には家族療法(短期療法)が効果がある場合が多いですし、実際のカウンセリングではそれらをミックスした形となることが殆どです。 エゴグラムテストなどの心理テストで、自分自身のパターンに気付いていただくことも可能です。 (エゴグラムは弊社ホームページの「交流分析 エゴグラムのページ」を、認知療法は「認知行動療法」のページを、応用行動分析は「応用行動分析(ABA)」のページをご参考ください。) こうやって書くと、なんか難しそうに聞こえますが、実際は悩み事を思ったままにお話していただくだけでOKです。 もちろん秘密厳守ですし、クライアントの気持ちを重視したカウンセリングですので心配は要りません。 言いたくない事は言わなくてかまいません。 ハート・コンシャスには女性のカウンセラーもいます。 玉田祐子 NPO日本次世代育成支援協会講師 NPOハート・コンシャス代表理事
 【場所・お申し込み方法等】
愛知県一宮市大志1丁目6-17ミヤタビル3階 TEL 0586-23-5575
(JRまたは名鉄一宮駅から東へ徒歩10分。)
料金 1回50分6000円(但し、前もってのご予約とお振込みが必要です)
9時~21時まで。日曜水曜は原則として休業
(事務所への電話受付は10時から16時まで) 完全予約制
メール、または電話でお申し込みの上、6000円をお振込みください。
なおWEBカウンセリングの場合は、電波やネット環境によって不安定となる場合がありますので、そういう場合は電話カウンセリングをお勧めします。
【場所・お申し込み方法等】
愛知県一宮市大志1丁目6-17ミヤタビル3階 TEL 0586-23-5575
(JRまたは名鉄一宮駅から東へ徒歩10分。)
料金 1回50分6000円(但し、前もってのご予約とお振込みが必要です)
9時~21時まで。日曜水曜は原則として休業
(事務所への電話受付は10時から16時まで) 完全予約制
メール、または電話でお申し込みの上、6000円をお振込みください。
なおWEBカウンセリングの場合は、電波やネット環境によって不安定となる場合がありますので、そういう場合は電話カウンセリングをお勧めします。
但し、ご予約が多いのと、カウンセラーは全国各地に講演やセミナーの講師としてに出張している為、当日すぐにカウンセリングを受けたいというご要望にはなかなか応じられていないのが現状です。 大変申し訳ありませんが、お客様のご都合と、こちらの空いている時間がマッチした時間にご予約をお願いしております。 また、カウンセリングはその前後の時間に余裕を設けて、じっくり落ち着いて行わなければできませんので、1日に5~6人とさせていただいております。 できるだけご希望の時間に合わせるよう努力いたしますが、ご希望の日時に時間が取れないこともございますので、ご理解ください。 (特に土曜日はかなり早めでないと取りにくい状況です。) なお、キャンセルは7日前から(土曜は14日前)キャンセル料(6000円全額)が発生しますのでご注意ください。 お申込みは玉田 tamada@heart-c.orgまで
NPOハート・コンシャスの活動状況
児童とスマホの問題についてお話しました
 東海テレビ「スイッチ」で、幼児や児童にスマホを見せることについてお話しました。
東海テレビ「スイッチ」で、幼児や児童にスマホを見せることについてお話しました。
福井県で「ネット・スマホ依存防止セミナー」の講師を務めました
 福井県坂井市教育委員会主催の「ネット・スマホ依存防止セミナー」の講師を務めました。
沢山の先生や教育に携わる方々に熱心に聴いていただき、また貴重な現場の情報をいただきました。
子どもたちの未来に少しでも貢献できましたら幸いです。
福井県坂井市教育委員会主催の「ネット・スマホ依存防止セミナー」の講師を務めました。
沢山の先生や教育に携わる方々に熱心に聴いていただき、また貴重な現場の情報をいただきました。
子どもたちの未来に少しでも貢献できましたら幸いです。
清州保健所の「自殺対策人材育成研修」
 愛知県県清州保健所の職員対象に「自殺対策人材育成研修」が開かれ、講師を務めました。
愛知県県清州保健所の職員対象に「自殺対策人材育成研修」が開かれ、講師を務めました。
一宮消防局で、「パワハラ防止」の講演
 愛知県一宮消防局の「パワハラ防止セミナー」で、NPOハート・コンシャスの鷲津が講師を勤めました。
愛知県一宮消防局の「パワハラ防止セミナー」で、NPOハート・コンシャスの鷲津が講師を勤めました。
お問い合わせはコチラへ!
![]() 電話番号: 0586-72-7880
電話番号: 0586-72-7880 ![]() 玉田 tamada@heart-c.org
玉田 tamada@heart-c.org